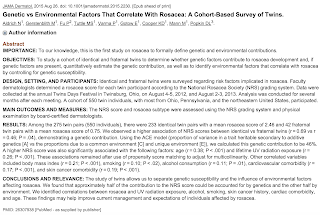「いままで通っていたクリニックがなくなってしまったんです」と言って受診される患者さんがときどきいらっしゃるのですが、みな一様にクリニックがなくなった理由がわからないといいます。新宿区(もっと大きなくくりで東京?)という場所柄なのか、はたまた医療崩壊が始まったのか…閉院あるいは休院した理由がわかるクリニックもありますが、一番の問題は医療と経営のバランスが難しいからでしょう。
とある医療法人は短期間の間に大きな医療クリニックを立て続けに開院したために、負債10億円で倒産したようです。昔は、医院や診療所(敢えてクリニックとは呼ばない)と言うと住宅街にぽつんとあったものです。私の祖父や祖母もそのような形態で開業していました。とくに商店街でもなく職住一体となった建物で、いわゆる「かかりつけのお医者さん(町医者)」でした。時代が進み、駅や商店街の近くの目立つところでクリニックを設立することが当たり前のようになり、医療コンサルタントと称する人たちによる「いわゆる一般的な商業的な経営理念を少しだけ医療向けに置き換えた経営スタイル」を模倣するクリニックや薬局のバックアップのもと医療モールで開業するという形態が中心となっています。
話は変わって、つい最近マクドナルドが経営不振による大規模な店舗閉鎖をおこないました。今回閉店した店舗が赤坂見附、六本木、池袋西口、駿河台などいつも混雑している店舗ばかりで、「なぜ閉店するのか」とツイッターなどSNSで疑問の声が上がっていました。これらの店は私も利用したこともあるのですが、昼時以外でもレジは長い行列でとても混んでいた印象があります。こんな一見流行っているようにみえる店舗が閉店に追い込まれたのは、「いくら高収益であっても人件費や家賃の高騰があるために黒字化が難しい」という切実な理由があったようです。とくに東京は2020年のオリンピックなどのイベントに加えて、海外からの観光客の増加や、TPPによる関税撤廃と円安による海外資本の流入により、家賃や物価もいままで以上にどんどん上昇していくでしょう。
この話と医療がなぜ関係しているのかというと、いま医療経営で成功の条件(私は違うと思っていますが)と思われている経営手法と関わりがあるからです。10億の負債をかかえた医療法人も駅ビルや駅前のモールに診療所を構えており、立地の良さからは高収益が期待されたと思われます。さらに最新の医療機器を備え、非常勤医師を多数雇っていたようです。綺麗な施設と最新の装置…私もそのような施設で仕事ができたらどんなに良いかと思います…が、実際に経営の立場から考えると非常に大変なことに気づきます。どんなに高収益であっても、駅前や新しいビルの家賃は更新のたびに高騰していきますし、非常勤医師をひとり雇うたびに1日あたり何十人もの多くの患者さんを診察しなくては、バイト料に見合った収入が得られません。そのために集患のための広告費はかさみ、診察が混んでくると看護師や事務員さんも増員しなくてはならなる…収益のために出費がかさむジレンマに陥ります。そうなるとせっかく地域医療のためにと開業しても診察のためではなく、経営のための自転車操業になってしまうのです。破産した医療法人は短期間のうちに複数のクリニック経営を展開するなど誤った選択をしてしまったのも問題なのでしょうが…。
それこそマクドナルドが「高収益でも黒字化が難しい」と大量閉店をおこなったように、医療の世界でも立地や集患だけでなく、地に足の着いた経営計画が求められていく時代になっているのでしょう(大変です)。とくに東京など大都市圏は人件費も家賃も高いため、今後もクリニックや医療法人破産のニュースが増えるかもしれません。これからは周囲(誰とは言いません)の甘いささやきや誘惑に惑わされることなく、背伸びをしないクリニック作りが大事なんだと思いました。うちは…街なかに地味にひっそりとやっている小料理屋のようなクリニックを目指しています。
2015年12月14日月曜日
2015年11月29日日曜日
Spike Wilner Trio - Live at Smalls
ニューヨーク、ウェスト・ヴィレッジ・7thアヴェニュー・サウスにあるジャズクラブ「Smalls」の共同経営者であり、ピアニスト、作曲家、ジャズ研究家など複数の肩書をもつスパイク・ウェルナーのトリオ盤。
トリオといってもピアノ、ベース、ドラムではなく、ピアノ、ベース、ギターであり、アート・テイタム、ナット・キング・コール、オスカー・ピーターソンなどでみられた、1930〜40年台あたりの古典的な編成である。このドラムレス・トリオはスパイク・ウェルナーの「ピアノが主役。ドラムやヴォーカルは入れない。」という経営方針にも現れているようです。アルバムではベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番「悲愴」第2楽章やスコット・ジョプリンの「マグネティック・ラグ」からジェローム・カーンやコール・ポーターのミュージカル曲(ジャズ・スタンダードとして知られた曲)をpopular themeとして変奏曲にしたりしています。ピアノは雄弁に語りかけたり、音の強弱を奏でたりすることなく、控えめな音と少ない音数でリズミカルに演奏しています。ピアノソロに優しく寄り添うベースとギターはときに絡みつくように音を重ねていくさまは非常に心地よく感じます。
クリニックのBGMとしても主張し過ぎず、うるさ過ぎずで最適です。クリニックには小さい子供から高齢の方まで受診していただいているため、(音楽的には卓越していたとしても)新しいジャズやコンテンポラリー・ミュージックは音が先鋭的になりやすいためBGMになりにくいのですが、このアルバムならいろいろな年代の人に楽しんでいただけるのではと思います。
ディスクユニオンのエサ箱(セール品ですごく安かった)にあったもの購入したのですが、とても聴き応えのあるアルバムでした。冬の夜なんかに最適の1枚です。
トリオといってもピアノ、ベース、ドラムではなく、ピアノ、ベース、ギターであり、アート・テイタム、ナット・キング・コール、オスカー・ピーターソンなどでみられた、1930〜40年台あたりの古典的な編成である。このドラムレス・トリオはスパイク・ウェルナーの「ピアノが主役。ドラムやヴォーカルは入れない。」という経営方針にも現れているようです。アルバムではベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番「悲愴」第2楽章やスコット・ジョプリンの「マグネティック・ラグ」からジェローム・カーンやコール・ポーターのミュージカル曲(ジャズ・スタンダードとして知られた曲)をpopular themeとして変奏曲にしたりしています。ピアノは雄弁に語りかけたり、音の強弱を奏でたりすることなく、控えめな音と少ない音数でリズミカルに演奏しています。ピアノソロに優しく寄り添うベースとギターはときに絡みつくように音を重ねていくさまは非常に心地よく感じます。
クリニックのBGMとしても主張し過ぎず、うるさ過ぎずで最適です。クリニックには小さい子供から高齢の方まで受診していただいているため、(音楽的には卓越していたとしても)新しいジャズやコンテンポラリー・ミュージックは音が先鋭的になりやすいためBGMになりにくいのですが、このアルバムならいろいろな年代の人に楽しんでいただけるのではと思います。
ディスクユニオンのエサ箱(セール品ですごく安かった)にあったもの購入したのですが、とても聴き応えのあるアルバムでした。冬の夜なんかに最適の1枚です。
2015年11月24日火曜日
グラッシュビスタやザガーロはなぜ高いのか?
今回は保険適応外治療として使用されている自費診療で処方される薬について考えてみました。皮膚科領域で現在、自費診療で発売している薬剤としては、「プロペシア(ジェネリックのフィナステリドも含む)」、「グラッシュビスタ」があり、発売延期となりましたが「ザガーロ」もその仲間です。
これらのなかでも「グラッシュビスタ」はまつ毛貧毛症、「ザガーロ」は男性型脱毛症(AGA)の薬として使用されます。点眼液と内服薬の違いがありますが、いずれも「ルミガン点眼液」、「アボルブ」という他の疾患に対する薬剤があります。「ルミガン点眼液」は緑内障・高眼圧症に対して保険適応がある点眼液です。まつ毛にこの点眼液が付着することでまつ毛が伸びたり、太くなる副作用が知られており、まつ毛を伸ばす目的で以前より美容クリニックなどで処方されていました。一方、「アボルブ」は前立腺肥大症の治療薬ですが、AGAの原因である5α-還元酵素Ⅰ型・Ⅱ型とも阻害するため、既発売である「プロペシア」(フィナステリド;Ⅱ型還元酵素のみ阻害)よりも治療効果が期待できると、泌尿器科・内科、AGAクリニックなどで処方されていました。
これらの薬に共通しているのは、本来の目的以外の治療効果に対して使用している点です。一般的に保険適応外と呼ばれるものは、海外では保険適用であっても本邦では未承認、あるいは治療効果については実証されていても認可されていない薬剤を使用することを指します。「ルミガン点眼液」によるまつ毛育毛や「アボルブ」によるAGA治療も大きな括りで言えば保険適応外となります。
このような薬が保険適応拡大ではなく、自費診療としてこれらの薬を(名前を変えてまで)発売することに至った経緯には幾つかの理由があると思います。①日本は高齢化社会となり医療費が逼迫している、②まつげ貧毛症やAGAの治療に医療保険を使うことで医療費がかさむことが予想される(これは保険を使用して治療を必要とする疾患か否かという意味合いもあると思います)、③保険適応外にも関わらず、保険病名として「緑内障」や「前立腺肥大症」と記載して処方する(これは違法です)ことが少なからずあるため、④保険適応外で使用した場合、重篤な副作用になった場合、医薬品副作用被害救済制度を受けられない(逆に言うと高額であるが「グラッシュビスタ」や「ザガーロ」は救済措置を受けることができる)、などが考えられます。
①②は医療費40兆円/年を超えることや、診療報酬改定のニュースが話題となっているため理解しやすいと思います。率直に言って、まつ毛貧毛症やAGAは命に関わるものではなく、かならずしも治療しなくてはいけない疾患ではない…ということを意味しているのでしょう。どうしても治療をしたければ自費でという流れです。
③は自費だと患者さんの費用負担が大きいので優しさで処方してあげる…と言うと聞こえは良いですが、保険診療でこれらの薬を処方し続けることは違法(厳密に言うと健康保険法違反)です。摘発されるリスクを犯しながら処方を続けることはできません。
④は副作用がない限り問題ないと思われがちですが、インターネットで並行輸入の医薬品を購入したり、院内処方で「ルミガン点眼液」や「アボルブ」をまつ毛貧毛症やAGA治療目的で購入した場合、それらの薬で問題が生じた時に保証されません。このことをどれだけのひとが理解しているのか、そのリスクを承知して購入しているか心配です。皮膚科医はスティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)や中毒性表皮壊死症(TEN)、薬剤過敏症症候群(DIES)などの重症薬疹(重篤な副作用)で苦しんできたひとを何人も診療しており、今まで報告がなくてもどのような薬剤でも重症薬疹を引き起こすリスクがあることを知っています。だからこそ、副作用で薬疹になったときに救済措置ができる「グラッシュビスタ」や「ザガーロ」を処方することで、このようなリスクを回避ができるようになったことは非常に大事だと思います。
ただ…金額設定はどのようにしておこなわれているのか、どうしてこの値段になのか?というところはわかりません(「ザガーロ」は「プロペシア」の1.6倍の効果があると宣伝しているので、仕入れ値も1.5倍ぐらいになっている?)。並行輸入や保険適応外処方(院内処方を含む)と張り合う値段とまではいかなくても、もう少し購入しやすい価格というのは検討されていなかったのでしょうか…薬剤には使用期限があるため、在庫を抱えるのは良くないですよね。
これらのなかでも「グラッシュビスタ」はまつ毛貧毛症、「ザガーロ」は男性型脱毛症(AGA)の薬として使用されます。点眼液と内服薬の違いがありますが、いずれも「ルミガン点眼液」、「アボルブ」という他の疾患に対する薬剤があります。「ルミガン点眼液」は緑内障・高眼圧症に対して保険適応がある点眼液です。まつ毛にこの点眼液が付着することでまつ毛が伸びたり、太くなる副作用が知られており、まつ毛を伸ばす目的で以前より美容クリニックなどで処方されていました。一方、「アボルブ」は前立腺肥大症の治療薬ですが、AGAの原因である5α-還元酵素Ⅰ型・Ⅱ型とも阻害するため、既発売である「プロペシア」(フィナステリド;Ⅱ型還元酵素のみ阻害)よりも治療効果が期待できると、泌尿器科・内科、AGAクリニックなどで処方されていました。
これらの薬に共通しているのは、本来の目的以外の治療効果に対して使用している点です。一般的に保険適応外と呼ばれるものは、海外では保険適用であっても本邦では未承認、あるいは治療効果については実証されていても認可されていない薬剤を使用することを指します。「ルミガン点眼液」によるまつ毛育毛や「アボルブ」によるAGA治療も大きな括りで言えば保険適応外となります。
このような薬が保険適応拡大ではなく、自費診療としてこれらの薬を(名前を変えてまで)発売することに至った経緯には幾つかの理由があると思います。①日本は高齢化社会となり医療費が逼迫している、②まつげ貧毛症やAGAの治療に医療保険を使うことで医療費がかさむことが予想される(これは保険を使用して治療を必要とする疾患か否かという意味合いもあると思います)、③保険適応外にも関わらず、保険病名として「緑内障」や「前立腺肥大症」と記載して処方する(これは違法です)ことが少なからずあるため、④保険適応外で使用した場合、重篤な副作用になった場合、医薬品副作用被害救済制度を受けられない(逆に言うと高額であるが「グラッシュビスタ」や「ザガーロ」は救済措置を受けることができる)、などが考えられます。
①②は医療費40兆円/年を超えることや、診療報酬改定のニュースが話題となっているため理解しやすいと思います。率直に言って、まつ毛貧毛症やAGAは命に関わるものではなく、かならずしも治療しなくてはいけない疾患ではない…ということを意味しているのでしょう。どうしても治療をしたければ自費でという流れです。
③は自費だと患者さんの費用負担が大きいので優しさで処方してあげる…と言うと聞こえは良いですが、保険診療でこれらの薬を処方し続けることは違法(厳密に言うと健康保険法違反)です。摘発されるリスクを犯しながら処方を続けることはできません。
④は副作用がない限り問題ないと思われがちですが、インターネットで並行輸入の医薬品を購入したり、院内処方で「ルミガン点眼液」や「アボルブ」をまつ毛貧毛症やAGA治療目的で購入した場合、それらの薬で問題が生じた時に保証されません。このことをどれだけのひとが理解しているのか、そのリスクを承知して購入しているか心配です。皮膚科医はスティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)や中毒性表皮壊死症(TEN)、薬剤過敏症症候群(DIES)などの重症薬疹(重篤な副作用)で苦しんできたひとを何人も診療しており、今まで報告がなくてもどのような薬剤でも重症薬疹を引き起こすリスクがあることを知っています。だからこそ、副作用で薬疹になったときに救済措置ができる「グラッシュビスタ」や「ザガーロ」を処方することで、このようなリスクを回避ができるようになったことは非常に大事だと思います。
ただ…金額設定はどのようにしておこなわれているのか、どうしてこの値段になのか?というところはわかりません(「ザガーロ」は「プロペシア」の1.6倍の効果があると宣伝しているので、仕入れ値も1.5倍ぐらいになっている?)。並行輸入や保険適応外処方(院内処方を含む)と張り合う値段とまではいかなくても、もう少し購入しやすい価格というのは検討されていなかったのでしょうか…薬剤には使用期限があるため、在庫を抱えるのは良くないですよね。
2015年11月17日火曜日
プロトピックで催奇形性?
あっという間に11月になり、2015年もあと少しとなってきました。クリニックはゆっくりにながら成長を続けている…はずです。これもひとえに受診していただける患者さまや支えてくれる家族・スタッフの方のおかげと感じています。
今回も皮膚科の話題をひとつ。プロトピック®軟膏についてです。一般名はタクロリムスといい、アトピー性皮膚炎に対して保険適応がある外用剤です。タクロリムス水和物は茨城県筑波山付近で採取された放線菌(Streptomyces tukubaensis)の代謝産物である免疫抑制剤で、経口薬(先発品はプログラフ®)は臓器移植・骨髄移植の拒絶反応や関節リウマチの治療で使用されてきました。その外用剤がプロトピック®軟膏となります。
プロトピック®軟膏は1999年(小児用は2003年)の発売からいろいろな論文により翻弄されてきた軟膏でもあります。①長期間外用するとリンパ腫(皮膚癌)になる、②催奇形性や胎児奇形の心配がある…などです。こんな話を聞かされれると外用するのが怖くなってしまうのですが、①②ともにちゃんとした解答があり、医師がきちんと使用方法を説明し使用方法を正しく守って外用すれば安心して使える外用剤なのですが、いまだにHPやブログの記事やYahoo知恵袋などの回答で「使用するのは危険」と書かれており、ちょっとかわいそうに思います。
①は「タクロリムス軟膏のマウス2年間塗布試験」が発端です。この実験では「タクロリムス軟膏を1日1回、2年間にわたり塗布した結果、タクロリムス血中濃度が上昇し、リンパ腫の発現が有意に上昇した」ものでした。この結果だけでは確かに皮膚癌リスクが高いかも…と思うのですが、マウスの皮膚はヒトよりも100〜200倍薄いため薬剤の吸収率が高くなること、マウスの寿命が約2年であるため、一生かけて塗布していること、マウスのリンパ腫発生頻度が高いことなどのバイアスがあり、現在ではヒトではそのようなリンパ腫を起こす血中濃度にはならず、癌の発生率も自然発生率と変わらないという論文が数多くあります。しかし、その後も小児の不適正な長期使用例で発癌率上昇の可能性の報告もあり、医師がプロトピック®軟膏の特性について理解せず処方することは非常に危険です。
②は「タクロリムスを経口投与したうさぎの実験」で催奇形性や胎児奇形の報告があり、プロトピック®軟膏に対するものではありません。しかし、薬剤師の方でも「長期外用により催奇形性や胎児奇形がおきる」と誤解されている方もまだいらっしゃるようで、「薬局で催奇形性のある薬剤と言われた」と患者さまから教えてもらうこともあります。短時間でいろいろ説明するため、簡潔に伝えるのは難しいのかもしれないですが、殊更に不安を煽るようなことはしないほうが良いのでは…と考えてしまいます。
プロトピック®軟膏は使用方法を熟知したひとが説明すれば、ステロイド長期投与による副作用を軽減できる外用剤なので、処方する側が説明をしっかりしていかなくてはと思います。(プロトピック®軟膏の利点・欠点もあるので、それは別の機会に説明します)
今回も皮膚科の話題をひとつ。プロトピック®軟膏についてです。一般名はタクロリムスといい、アトピー性皮膚炎に対して保険適応がある外用剤です。タクロリムス水和物は茨城県筑波山付近で採取された放線菌(Streptomyces tukubaensis)の代謝産物である免疫抑制剤で、経口薬(先発品はプログラフ®)は臓器移植・骨髄移植の拒絶反応や関節リウマチの治療で使用されてきました。その外用剤がプロトピック®軟膏となります。
プロトピック®軟膏は1999年(小児用は2003年)の発売からいろいろな論文により翻弄されてきた軟膏でもあります。①長期間外用するとリンパ腫(皮膚癌)になる、②催奇形性や胎児奇形の心配がある…などです。こんな話を聞かされれると外用するのが怖くなってしまうのですが、①②ともにちゃんとした解答があり、医師がきちんと使用方法を説明し使用方法を正しく守って外用すれば安心して使える外用剤なのですが、いまだにHPやブログの記事やYahoo知恵袋などの回答で「使用するのは危険」と書かれており、ちょっとかわいそうに思います。
①は「タクロリムス軟膏のマウス2年間塗布試験」が発端です。この実験では「タクロリムス軟膏を1日1回、2年間にわたり塗布した結果、タクロリムス血中濃度が上昇し、リンパ腫の発現が有意に上昇した」ものでした。この結果だけでは確かに皮膚癌リスクが高いかも…と思うのですが、マウスの皮膚はヒトよりも100〜200倍薄いため薬剤の吸収率が高くなること、マウスの寿命が約2年であるため、一生かけて塗布していること、マウスのリンパ腫発生頻度が高いことなどのバイアスがあり、現在ではヒトではそのようなリンパ腫を起こす血中濃度にはならず、癌の発生率も自然発生率と変わらないという論文が数多くあります。しかし、その後も小児の不適正な長期使用例で発癌率上昇の可能性の報告もあり、医師がプロトピック®軟膏の特性について理解せず処方することは非常に危険です。
②は「タクロリムスを経口投与したうさぎの実験」で催奇形性や胎児奇形の報告があり、プロトピック®軟膏に対するものではありません。しかし、薬剤師の方でも「長期外用により催奇形性や胎児奇形がおきる」と誤解されている方もまだいらっしゃるようで、「薬局で催奇形性のある薬剤と言われた」と患者さまから教えてもらうこともあります。短時間でいろいろ説明するため、簡潔に伝えるのは難しいのかもしれないですが、殊更に不安を煽るようなことはしないほうが良いのでは…と考えてしまいます。
プロトピック®軟膏は使用方法を熟知したひとが説明すれば、ステロイド長期投与による副作用を軽減できる外用剤なので、処方する側が説明をしっかりしていかなくてはと思います。(プロトピック®軟膏の利点・欠点もあるので、それは別の機会に説明します)
2015年10月30日金曜日
酒さの原因はなに?リスク回避法は?
本当に久しぶりのブログです。今回は皮膚科らしい学術的なお話をしたいと思います。
「酒さ」は血管拡張することで鼻や顔が赤くなり、あたかもお酒を飲んだような赤い顔になってしまう病気です。進行するとにきびのような赤い丘疹ができ、なかなか治らない慢性疾患としても知られています。当クリニックでは酒さ治療としてロゼックスゲル®(メトロニダゾール)外用などを含めた内服・外用治療ならびにをおこなっておりますが、根治に至ることが難しい疾患でもあります。
そんな「酒さ」はどんな原因でできるのか…そんな疑問に答えてくれる論文が最近発表されたので、エッセンスをお伝えしたいと思います。JAMAというアメリカの著名な皮膚科雑誌に掲載された論文で、18〜80歳までの一卵性双生児233組、二卵性双生児42組を対象に病歴と生活習慣についての調査をおこない、その結果をコホート研究(疾病発生と要因の関連性を調べる観察的研究のこと)にてまとめています。
結果を簡単にまとめると、46%が遺伝に関与しており、生活習慣では紫外線暴露(日焼け)、加齢が大きく相関しています。その他、肥満(BMI)、喫煙、飲酒、心疾患、皮膚がんなども関連しているそうです(肥満、心疾患の因果関係ははっきりしていません)。
「酒さ」は遺伝や加齢が大きく関与している疾患ですが、日焼け、喫煙、飲酒などの生活習慣を改めることでリスク回避できる可能性があります。もし「酒さ」と診断された、あるいは家族に「酒さ」と診断された人がいる場合、日焼け、喫煙、飲酒を控えることが大事です。
[参考文献]
N. Aldrich: Genetic vs Environmental Factors That Correlate With Rosacea: A Cohort-Based Survey of Twins: JAMA dermatology. 2015
「酒さ」は血管拡張することで鼻や顔が赤くなり、あたかもお酒を飲んだような赤い顔になってしまう病気です。進行するとにきびのような赤い丘疹ができ、なかなか治らない慢性疾患としても知られています。当クリニックでは酒さ治療としてロゼックスゲル®(メトロニダゾール)外用などを含めた内服・外用治療ならびにをおこなっておりますが、根治に至ることが難しい疾患でもあります。
そんな「酒さ」はどんな原因でできるのか…そんな疑問に答えてくれる論文が最近発表されたので、エッセンスをお伝えしたいと思います。JAMAというアメリカの著名な皮膚科雑誌に掲載された論文で、18〜80歳までの一卵性双生児233組、二卵性双生児42組を対象に病歴と生活習慣についての調査をおこない、その結果をコホート研究(疾病発生と要因の関連性を調べる観察的研究のこと)にてまとめています。
結果を簡単にまとめると、46%が遺伝に関与しており、生活習慣では紫外線暴露(日焼け)、加齢が大きく相関しています。その他、肥満(BMI)、喫煙、飲酒、心疾患、皮膚がんなども関連しているそうです(肥満、心疾患の因果関係ははっきりしていません)。
「酒さ」は遺伝や加齢が大きく関与している疾患ですが、日焼け、喫煙、飲酒などの生活習慣を改めることでリスク回避できる可能性があります。もし「酒さ」と診断された、あるいは家族に「酒さ」と診断された人がいる場合、日焼け、喫煙、飲酒を控えることが大事です。
[参考文献]
N. Aldrich: Genetic vs Environmental Factors That Correlate With Rosacea: A Cohort-Based Survey of Twins: JAMA dermatology. 2015
登録:
投稿 (Atom)